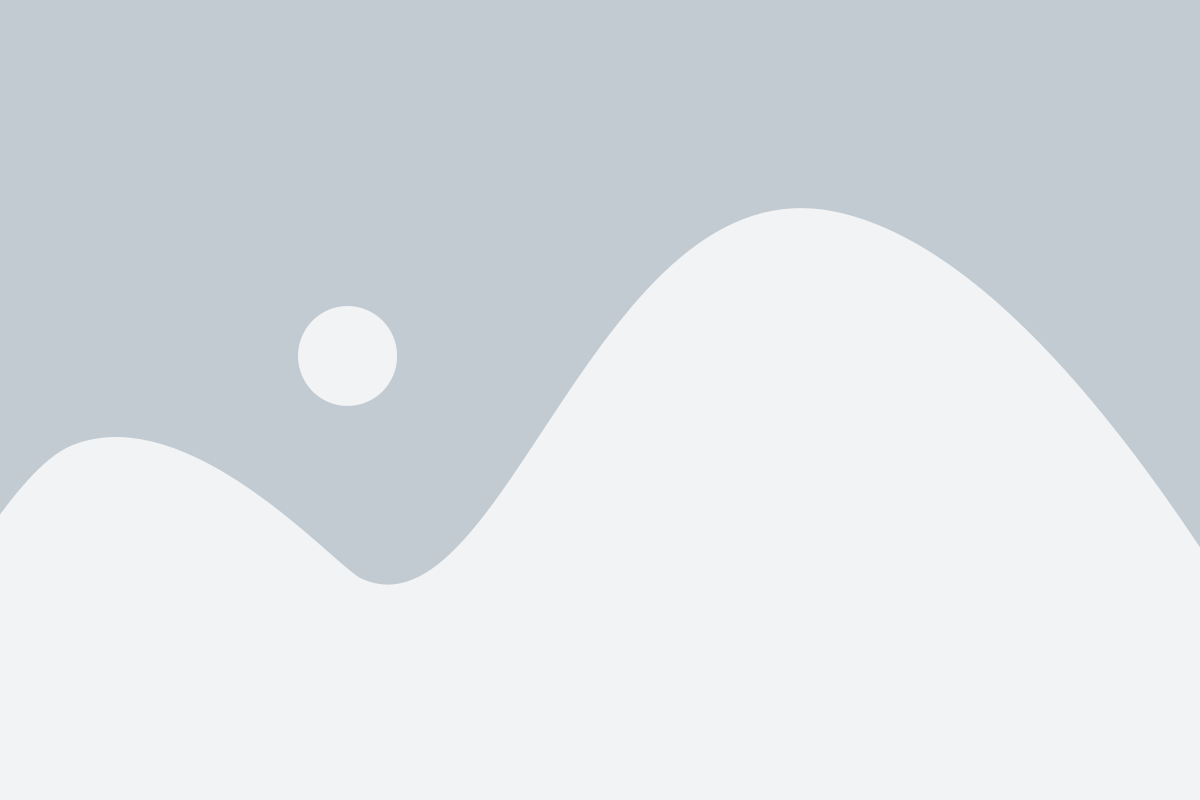もろい材料が使われる事情
前回、補修屋さんの仕事品質に対する不満を持つ現場監督さんのお話をしました。
補修材がボロボロになり取れてしまうというご不満でしたが、
具体的にはどのような状態になってしまうのでしょうか。
この点は、キズなどのリペアをご依頼される一般の入居者様も気にかける点の一つかと思います。
「以前の補修跡が取れてきて、気になっている。」
「もう一度直しても同じようにすぐ取れてしまったら嫌だな」
そのようにお悩みのお客様も多くいらっしゃいました。
補修材について考察する前に、なぜその補修材が使われたのか考えてみましょう。
補修材は、「補修」という言葉から「簡易的」「一時しのぎ」的に使用するイメージを持たれることも多いのですが、
実際には、ピンからキリまで といったところでしょうか。
良い材料もあれば、それほどでもない材料まで、玉石混淆というのが実態です。
ただし、何が良くて、何が悪いかは、評価する人の立場によって変わるため、
施工業者には良くても、入居者の方からは悪い評価になる材料・工法も存在します。
これは、効率重視で品質軽視と言われても仕方無いのですが、
そうしないと現場が回らない・人が育成できない
という事情が影響している事実もあります。
凹みを埋める樹脂には簡単に埋められるDIYタイプの物があるというのは
以前お話しましたが、
補修業界でも「簡単に」施工できる材料は重宝される傾向があります。
ただし、DIY材と同様、耐久性は低くなることが多くなり、これが品質に
対する問題を引き起こす一因となっています。
施工業者側は、この問題をどう考えているのでしょうか。